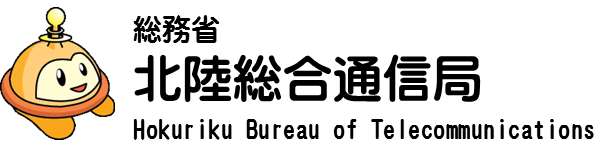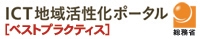HICC
北陸情報通信協議会

HOME ≫ 安心・安全部会 (ICT安心安全部会に... ≫
安心・安全部会
| ■ 活動概要 | 平成23年の東日本大震災をはじめ、最近は各所で災害等が発生しているが、その教訓の一つとして住民に対し、災害情報をいかに早急かつ正確に提供できるかが大きな課題として浮き上がっています。 災害情報の提供においては、ICTを利活用した伝達手段が有効であると認められていますが、国民生活の安心・安全のさらなる向上への一助として、北陸地域における効率的なICTによる情報伝達方法について検討し、有用なシステムについては、その導入に関わる諸課題について情報共有を図るとともに、北陸地域への導入促進の可能性を模索します。 |
| ■ 部会長 | 金沢大学 理工研究域環境デザイン学科 教授 宮島 昌克 |
| ■ メンバー | 当協議会の26団体・個人により構成 |
■活動状況
| 第18回会合 平成31年3月6日 |
北陸情報通信協議会 安心・安全部会(部会長 宮島 昌克 金沢大学教授)は、平成31年3月6日(水)に金沢広坂合同庁舎 1階 大会議室において、平成30年度の最終回である4回目(通算18回目)の会合を開催しました。
今回の部会では、平成31年の雪対策とICT利活用取組状況の報告と、平成30年度の安心-安全部会活動報告として「雪害等への的確な対応等に資する情報伝達、情報提供のあり方に関する報告書」をとりまとめました。 はじめに、平成31年今冬は昨年に比べ暖冬となり、降雪量はかなり少ないものでしたが、昨年の雪害を踏まえ大雪への備えとして新たにとった対策について構成員から報告があり、住民への情報発信や周知の強化への取組が挙げられました。具体的には、防災アプリを積極的に活用し、気象情報とは別に、各地方自治体が住民に周知したい情報を多く発信できるよう見直しを行っていることや、除雪車にGPSを搭載して除雪の位置を把握できるように進めていると説明がありました。 そして、安心-安全部会は、北陸地方の大雪の特徴や平成30年大雪による被害状況とその対 応、見出された課題についての検討を踏まえ、ICTによる課題解決が可能な事項と雪害対策として各主体が取り組むべき事項を抽出し、降雪時における情報伝達体制、情報提供イメージとして示した「雪害等への的確な対応に資する情報伝達、情報提供のあり方に関する報告書」(平成30 年度安心-安全部会報告)をとりまとめました。 最後に、宮島部会長は、雪害は地震とはスピード感は違うものであるが、情報伝達、情報受信の災害に関わるやりとりは共通しており、大雪も災害だと認識して、地震と同じような考え方で準備をして対策を行うことが極めて重要であるとして、これまでの安心-安全部会活動を締めくくりました。 |
| 第17回会合 平成30年12月4日 |
北陸情報通信協議会 安心・安全部会(部会長 宮島 昌克 金沢大学教授)は、平成30年12月4日(火)に石川県文教会館において、今年度3回目(通算17回目)の会合を開催しました。 今回の部会では、雪害に対して各主体が取り組むべき事項を検討するため、他の地域の雪害対策の取組事例を参考にしながら、降雪時における雪害の「予防期」「応急期」及び、「復旧期」において、各主体が取るべき雪害対策について討論を行いました。 はじめに、弘前市都市環境部 スマートシティ推進室主幹 樋口 英之 氏から、「弘前型スマートシティ構想と雪対策」と題して講演があり、統合型GIS(地理情報システム)と除雪車両に搭載したGPS情報の連携を図ることで、情報公開と効率的な除排雪作業の出動状況や気象状況を提供している「除雪管理システム」の紹介がありました。また、弘前市では、除雪作業距離は約1,000kmであり、 一般除雪は深夜 1時から早朝6時までと限られた時間で行う必要があることから、除雪グレーダや除雪ドーザ等で道路脇に雪をかき分ける作業を行う他、午前0時の段階で今後10㎝以上の降雪が見込まれる場合や早朝の降雪には、交通状況や作業時間を考慮し対応していると説明がありました。 次に、第16回会合で抽出したICTによる課題解決が可能な事項である「通信が継続できる体制、対策の確保 」、「情報集約の効率化、正確さ、迅速化」、「多様な情報伝達方法」及び、「Webサイトのアクセス集中対策」について、各主体が取り組むべき事項について検討を行いました。具体的には、関係機関との連携、大雪に係る業務継続計画(BCP)の策定、テレワークの導入、地域ポータルサイトの構築、データ放送の活用等、大雪に備えた準備を整えておくことの必要性について確認しました。 また、構成員から、「平成30年大雪」の際に見出された課題を踏まえ、平成31年の冬に向けてGPSを活用した除雪作業の検討、避難所における備蓄品の見直しなどを実際に行っていることの紹介や、大雪時の実体験から、コミュニティFMの情報発信が有効であると意見がありました。 最後に、宮島部会長から今部会の総括として、大雪を災害としてとらえ、雪害対策は、大地震等その他の災害においても有効な手段であり、災害と同様の対応をしていくことが重要だとまとめられました。 次回の部会では、各主体からの「平成31年大雪」に対するICT利活用の取組状況についての報告を受けるとともに、雪害などへの的確な対応に資する情報伝達、情報提供のあり方のとりまとめを行います。 |
| 第16回会合 平成30年10月1日 |
北陸情報通信協議会 安心・安全部会(部会長 宮島 昌克 金沢大学教授)は、平成30年10月1日(月)に石川県政記念しいのき迎賓館において、今年度2回目(通算16回目)の会合を開催しました。 今回の部会では、雪害などへの的確な対応に資する情報伝達、地域住民等への情報提供のあり方について検討するため、「ICTを活用した雪害対策の先進的な取組事例」について紹介した講演を聞き、その後、「平成30年(2018年)大雪」による被害状況と対応、見出された課題について話し合い、ICTによる課題解決が可能な事項の抽出を行いました。 はじめに、(一財)日本気象協会の平松 信昭 氏から「ICTを活用した道路気象サービス」と題して、接近する雨雲の内部構造(粒子判別)を観測する「X-MPレーダー」と、協会「独自の雲物理過程予測モデル」の比較を行うことで、高精度の気象予測結果を得ることが可能であると説明がありました。 また、DOMINGO(データ指向型モビリティ情報生成グループ)プロジェクトでは、時空間的に混在する多種多様なデータの融合分析により、災害リスクを検知・評価する技術開発や減災・避難支援計画に資するための情報提供システムの構築に向けた研究に着手しており、プローブデータ(車の位置情報や速度情報)と気象データ(降雪・吹雪の分布)から交通障害が発生・拡大する様子を解析していることが紹介されました。 次に、京福バス(株)高橋 和幸 氏から「京福バスナビシステムと2018大雪への対策」と題して、無線通信やGPSを利用して収集したバスの位置情報をスマートフォン等によってリアルタイムで確認することができる「京福バスナビ(新バスロケーションシステム)」の紹介がありました。 バス専用レーンの減少等で、定時制の確保が難しい中、利用者の信用性を高める上で「京福バスナビ」が大きな役割を果たしていることや、平成30年1月では急遽バスを運休せざるを得ない状況となり、利用者への情報伝達が満足に行き届かなかったこと、2月には、バス車庫の除雪が困難となりバスの運休が長期化したことを踏まえ、この経験から、「運休」に関する事前告知がいかに大切であるか認識し、今後の大雪の対応策として、状況に応じた「計画運休」の実施が非常に重要であると説明されました。 最後に、構成員から情報提供された「平成30年大雪による被害状況と対応、見出された課題」を基に意見交換を行いました。 大雪ならではの課題として「職員が出勤できず、業務に支障」「情報が多岐にわたり、入手方法と迅速な周知に課題」等が挙げられ、それらの改善策としてICTによって解決可能な事項について検討を進め、その結果以下の4項目を抽出しました。
【ICTによる課題解決が可能な事項】 ■情報集約の効率化、正確さ、迅速化 ■多様な情報伝達方法 ■Webサイトのアクセス集中対策 |
| 第15回会合 平成30年8月21日 |
北陸情報通信協議会安心・安全部会(部会長 宮島 昌克 金沢大学教授)は、平成30年8月21日(火)に金沢商工会議所において、今年度最初(通算15回目)の会合を開催しました。 当部会では、これまで東日本大震災をはじめ、北陸地域で発生した大規模災害時における情報伝達の実例、北陸地域に地理的条件が類似した都道府県の情報伝達手段の現状把握を踏まえ、北陸地域におけるICTを活用した災害時の、市町村から住民への情報伝達手段に関する検討を行ってきました。 今年度は、平成30年1月から2月の記録的な大雪(以下「平成30年大雪」)を受け、それにより生じた諸課題についてICTの視点から検証することとし、雪害などへの的確な対応に資する情報伝達体制、通勤・通学者のほか地域住民等への情報提供のあり方について検討を行うこととしたものです。 今回は、構成員を追加募集して、新たに5団体を加えた26団体の部会構成員により開催しました。会合では、構成員の紹介の後、今年度の部会の進め方について事務局から提案され、活動スケジュールと検討事項が承認されました。 その後の講演では、初めに国土交通省北陸地方整備局 道路部 道路管理課長 木村 祐二 氏から「北陸地域の雪害対策」について、平成29年11月から平成30年3月までの雪の記録、整備局の取組等が紹介され、冬期の交通確保対策について説明がありました。また、ETC2.0を活用し、大雪に関する通行状況や通行止めに関する情報、降雪状況が確認できるカメラ画像等を道路利用者に提供しており、今後もICTを使った取組を積極的に進めていくと説明がありました。 次に、気象庁金沢地方気象台 次長 常盤 実 氏からは「北陸地方の大雪」と題して、平成30年大雪が平野部を中心に大雪となる「里雪」となった原因について、「地上天気図」、「衛星赤外画像」、「気象レーダー」のアニメーションによる詳しい説明がありました。金沢地方気象台では、12月から3月の期間は独自に降雪量予想を行い、1日2回HPに掲載していることも紹介されました。
|
| 第14回会合 平成30年3月16日 |
第14回会合は、部会でとりまとめた「北陸地域におけるICTを活用した災害時の市町村から住民への情報伝達手段に関する報告書」のなかで課題としてあげられた「情報通信基盤の耐災害性の向上」及び「情報収集業務の効率化・迅速化」ついて考察を行いました。 会合では、部会構成員の日本電気株式会社から「クラウド型防災情報提供システムの特徴と導入事例・インターネットを介した情報収集ステム」と題し、オンプレミス型、クラウド型、ハイブリッド型それぞれの防災情報提供システムの特徴を、耐災害性(建物、通信回線)、導入コスト、維持コスト、システム構築面(構築期間、システム連携)、拡張性(HWリソースの追加、機能の追加、利用者の追加)、運用性・保守性(セキュリティ、システム障害対応、アクセシビリティ)などの観点で比較、紹介するととともに、SNSから災害情報をいち早くキャッチする"DISAANA/D-SUMM“の紹介がありました。 次に、株式会社パスコから、予測される自然災害のリスクを事前に提供する災害リスク情報サービス「DR-Info(ディーアールインフォ)」のほか、防災・減災に関する支援システムについての紹介がありました。 続いて、現構成員の体制となった平成29年2月の第12回会合から現在までの部会活動について報告がされました。 今年度は、取りまとめた報告書において課題とされた事項等について、それらの課題解決に資するため最近の技術動向や先進事例の研究、防災対策設備などの現地視察を行いました。 平成26年2月から約4年間にわたり、災害時における住民への情報伝達手段に関する検討、報告書の作成、出された課題への対策事例の紹介など部会活動を進めてきた結果、一定の成果が得られたことから、今回の会合をもって本検討について一区切としました。 次年度は、今季の記録的な大雪を受け、今季の大雪により生じた諸課題についてICTの視点から検証することとし、雪害などへの的確な対応に資する情報伝達体制、地域住民等への情報提供のあり方について検討していくこととし承認されました。 |
| 第13回会合(災害対応施設等見学会) 平成29年11月15日 |
第13回会合は、災害対策が施されている施設の設備等について見識を深めるため、富山県内の災害対応施設及び防災関連施設の見学会を開催し16名が参加しました。 災害対応施設として津波や地震、落雷など様々な自然災害への対策が施されている「株式会社パワー・アンド・IT」を、防災関連施設として地震や風水害、雪害などの自然災害が発生した際の防災活動の拠点としての役割を担っている「国土交通省北陸地方整備局富山防災センター」を見学しました。 株式会社パワー・アンド・ITは、北陸電力(株)と(株)インテックが共同出資し設立したデータセンター事業者で、津波の心配がない海岸線から離れた強固な地盤に立地している施設を有しています。耐震対策では、震度7相当の地震でも機能を損なわないよう5種類の免震装置を設置、停電対策では電源設備について、異なる変電所から2系統により受電するとともに、無停電電源装置および非常用発電機をそれぞれN+1の冗長構成で設置、加えて最高の保護レベルの耐雷対策も講じられており、職員の方からこれらの各設備について説明を受けました。 国土交通省北陸地方整備局富山防災センターは、災害が発生した時、地域の災害対応を迅速にかつ的確に行うため、地域防災の拠点としての役割を担っている施設であり、災害対策機械、資機材の管理、運営などを行っているほか、災害対策本部の代替施設としての機能も有しています。センターでは、職員がセンターの概要の説明や災害現場における活動の模様を映像で紹介いただいたほか、災害対策車両格納庫の排水ポンプ車、 照明車、 遠隔操縦ショベルなどを見学し各車両の用途や特徴について説明を受けました。 |
| 第12回会合 平成29年8月31日 |
第12回会合は、昨年、部会でとりまとめた「北陸地域におけるICTを活用した災害時の市町村から住民への情報伝達手段に関する報告書」のなかで出された課題のひとつである「停電対策」を取り上げ、防災拠点や通信設備等の停電対策の現状と対策手法について考察を行いました。 会合では、構成員から庁舎施設やCATV会社の局舎設備、伝送路設備の停電対策について説明があり、発電室への浸水など想定される災害への対応や備蓄燃料の劣化対策など意見交換を行いました。 また、停電地域における画像等情報伝送のツールとして有効な可搬型の無停電エリアネットワーク機器の紹介のほか、8月27日に開催された福井県総合防災訓練において実施した臨時災害放送局や臨時地デジ中継局、公共ブロードバンド移動通信システムを用いた情報伝達訓練などの紹介がありました。 会合後、「停電対策」について先進的な取組をされている2社から、各社の取組についてご紹介いただく「ミニ講演会」を開催し、(株)PALTEKから自社が推進しているプロパンガス発電機による停電対策システムについて、本田技研工業(株)から燃料電池自動車と外部給電器を組み合わせた電源供給システムについてそれぞれご紹介いただきました。 |
| 「災害時の通信・放送の確保」講演会 平成29年6月16日 |
部会活動の取り組みとして、KKRホテル金沢において「災害時の通信・放送の確保」講演会を開催しました。講演会には、国、自治体、電気通信事業者、放送事業者など約120名が参加しました。 講演:「災害時における通信・放送の確保への取組」 講師:総務省北陸総合通信局防災対策推進室 室長 瀬高 隆裕 氏 講演:「KDDIにおける災害対策に関するさまざまな取組」 講師:KDDI株式会社技術企画本部電波部企画・制度グループ マネージャー 遠藤 晃 氏 |
| 第11回会合 平成29年2月7日 |
「北陸地域におけるICTを活用した災害時の市町村から住民への情報伝達手段に関する報告書」を取りまとめたことから、今回の会合からは、報告書の中で課題とされた事項等について、最近の技術動向や事例研究の成果発表などを通じてその解決方策を紹介するとともに、災害に強い情報伝達システムの実現に向けた検討を行うこととし、構成員を再募集し、新たな構成により開催しました。 会合では、構成員の紹介の後、今後の部会の進め方について事務局から提案され、承認されました。 会合終了後、北陸総合通信局との共催により、「災害時における情報伝達手段に関するセミナー」を開催しました。 |
| 平成28年11月15日 | 「北陸地域におけるICTを活用した災害時の市町村から住民への情報伝達手段に関する報告書」 をホームページにて公開。 報告書全文はこちら (約2.5MB) 概要版はこちら(約250KB) |
| 第10回会合 平成28年7月8日 |
第9回会合で提案した「北陸地域におけるICTを活用した災害時の市町村から住民への情報伝達手段に関する報告書(案)」について、その後に発生した熊本地震に関する概要等を追記したものを最終版の報告書とすることとなりました。報告書の最終版は、平成28年10月を目途に作成し、当協議会ホームページにて公表する予定です。 次に、昨年度香川県坂出市で行われたLアラートと防災行政無線を連携させた「情報入力端末機能拡張に伴う行政無線卓と県防システムへの同報通知の実証実験」の概要とその成果について、日本電気(株)の中川 哲夫 氏から説明をいただきました。 今回の報告書の完成をもって、現在、部会で検討している課題については一区切りすることとなりますが、今後、事務局から新たな課題を提起し、その解決に向けて検討を行う場として部会を継続していくことを確認しました。 なお、部会終了後、協議会会員を対象に、部会長の金沢大学教授の宮島 昌克氏から「熊本地震の概要と被害の特徴」と題して講演をいただき、現地調査に基づく被害状況やドローンで空撮した家屋倒壊の様子や断層被害について説明を受けました。 |
| 第9回会合 平成28年3月31日 |
最初にパナソニックシステムネットワークス(株)システムインテグレーションセンター公共システム部担当課長 野仲 様から、同社が開発した家庭用のテレビを活用した情報伝達手段のうち、プッシュブル型パーソナルサイネージシステムについて実際の機器の展示を交えてご紹介いただきました。 同システムは自治体と地域をインターネットで結び、災害の程度に応じ、テレビ未視聴(スタンバイ状態)でも強制的に情報告知を行うことが可能であり、平常時にあっては、ゴミの回収日や冠婚葬祭情報など、地域に密着した情報を送信できるようになっています。説明の中では、実際に活用している自治体の例も交えながら、わかりやすく解説をいただきました。 次に第8回会合で、提示した骨子をもとに作成した「ICTを活用した災害時における市町村から住民への情報伝達手段に関する報告書(案)」について事務局から提案を行いました。 本案については、部会メンバーから修正意見等をいただいた後、最終案として確定することとしています。 |
| 第8回会合 平成26年12月25日 |
第8回会合では、宮島部会長より「今年の自然災害を振り返る」と題し、部会長が広島豪雨と長野県北部で発生した地震について、現地調査をされた内容を撮影画像等を交えてお話をいただきました。 2つの自然災害に関する概要は以下のとおり。 <広島豪雨> 当日の気象データをもとに、一時間毎の降水量変化を分析したところ、前日19時~23時の間に比較的強い雨が降っていたが、23時~1時の間は雨が止み、1時~2時にかけて一気に80mm/hの雨となった。徐々に降水量が増加した2013年の伊豆大島と比べても、今回は一旦止んだことと深夜だったために土砂災害の予想は難しかったと考えられる。 <長野県北部の地震> 11月に発生したこの地震は幸いなことに死者が出なかったため、正式な地震名とならなかったが、長野県では「神城断層地震」と呼ばれている。 震度は最大6弱となっているが、現地で被災状況をみるともっと大きかったのではないかと思われる。震度は地震計が設置される地盤に影響されるので、震度だけで判断してはいけない。 |
| 防災関係者等による説明会 平成26年8月19日 |
宮島部会長が座長を務める「石川県市町防災担当、放送事業者によるLアラート導入検討連絡会」と共催で、防災関係者等による説明会を開催しました。 演題及び説明者 |
| 第7回会合 平成26年4月11日 |
前回から「災害情報伝達手段の多様化、多重化の在り方」についての検討を行っており、今回は、富山県及び福井県の2つのケーブルテレビ関係団体から報告を受けました。 次に、(株)ケーブルテレビ若狭小浜 事業部長 武倉 様と同社制作課長 重田 様より、平成25年9月に発生した台風18号における住民への伝達対応状況について、被災以降、住民からの様々な要望を検討し、同年12月に災害緊急放送に関する相互協定を結び、小浜市庁舎内に専用スタジオを置いて緊急時に3人体制をとること、国土交通省と福井県が提供している河川カメラと水位情報の静止画像を放送する等の取組が報告されました。 2つのケーブルテレビ関係団体の報告の後、報告事例を参考にしながら、活発な議論を行いました。 |
| 第6回会合 平成26年2月7日 |
安心・安全部会では、第6回会合から、新たな構成員で「災害情報伝達手段の多様化、多重化の在り方」についての検討を行うこととしており、今回は、自然災害を受けた北陸管内の3つの自治体から報告を受けました。 ○「平成25年9月に発生した台風18号での被災状況と住民の連絡 ○「平成25年台風18号における住民への情報伝達手段」と「災害情報等に関する住民実態アンケート調査結果」について 以上3つの自治体の報告終了した後、報告事例を参考にしながら、活発な議論を行いました。 |
| 第5回会合 平成25年6月26日 |
「民間クラウドサービス活用公共情報コモンズ導入モデル」検討ワーキンググループがとりまとめた実証実験報告書について確認した後、これを含めて部会がこれまで調査検討してきた成果をとりまとめたものとして、「公共情報コモンズの導入に関する報告(案)」が提案され、審議の結果、承認されました。 「民間クラウドサービス活用公共情報コモンズ導入モデル」 本報告では、「クラウド活用モデル」は、都道府県等の防災情報システムの改修の有無に関わらず、「公共情報コモンズ」を導入することができる極めて有用な接続モデルであるとともに、操作性や機能面で「コモンズエディタ」より優れていると評価できることなどについて提言が行なわれています。 |
| 第2回WGグループ 平成25年6月6日 |
第1回会合において確認した民間事業者が提供するクラウドサービス スを活用した公共情報コモンズ導入モデル(以下「クラウド活用モデル」)の実証実験について、その実施内容を確認するとともに、参加した自治体及び放送事業者からのアンケート結果に基づいて、クラウド活用モデルに対する意見、評価等の収集、分析を行いました。 |
| 第2回合同実証実験 平成25年5月30日 |
「民間クラウドサービス活用公共情報コモンズ導入モデル」の第2回合同実証実験を実施しました。 この実験は、民間のクラウドサービスを活用することによって、『公共情報コモンズ』の使い勝手を改善し、かつ、メリットを高めるため、新たなモデルの提案したもので、実際の情報入力の操作を通じて、このモデルの有効性を実感し、評価してもらうため実施したものです。 実験には、石川県及び石川県内の7市(金沢市、七尾市、小松市、かほく市、白山市、能美市、野々市市)の防災担当職員と県内の民放テレ各社が参加し、台風による大雨を想定した具体的な災害情報入力シナリオに従って、情報の入力、表示、閲覧等を行い、操作性や機能面の検証と評価をしていただきました。 実験終了後に行われた意見交換とアンケートでは、実験に参加した7市から、「このモデルはコモンズエディタより使い易い」、「実際に導入する場合は、今回の民間クラウドサービス活用モデルを使いたい」とのご意見がありました。 また、今後、解決してほしい課題として、「情報の入力画面において、入力履歴を活用できる機能を追加してほしい」、「コモンズへ送信する前に送信内容を入力画面で再確認できる機能を追加してほしい」などのご意見が出されました。 |
| 第1回WGグループ 第1回合同実証実験 平成25年5月9日 |
「民間クラウドサービス活用公共情報コモンズ導入モデル」検討ワーキンググループ(以下「検討WG」)を設置し、第1回会合を開催するとともに、併せて、第1回合同実証実験を実施しました。 検討WGは、安心・安全部会が昨年12月にとりまとめた「公共情報コモンズの導入に関する中間報告」を踏まえ、災害時の情報共有伝達基盤となる「公共情報コモンズ」の自治体への導入を促進するため、民間事業者が提供するクラウドサービスを活用した公共情報コモンズ導入モデル(以下「クラウド活用モデル」)の実証実験を行い、その有効性を検証するために設置したもので、第1回会合において、検討WG及び実証実験の概要・スケジュール等を確認しました。 引き続いて開催された第1回合同実証実験では、実証実験の概要等についての説明後、石川県及び石川県内の7市(金沢市、七尾市、小松市、白山市、能美市、かほく市、野々市市)の防災担当職員の参加を得て、実際の災害を想定したシナリオに沿い、クラウド活用モデルを利用して公共情報コモンズへの情報発信を行い、操作性等を検証しました。 |
| 第4回会合 平成24年12月12日 |
安心・安全部会がこれまで調査検討してきた成果をとりまとめたもの として、「公共情報コモンズの導入に関する中間報告(案)」が提案され、承認されました。本中間報告の特徴、ポイントは、次のとおりです。 公共情報コモンズの導入に関する中間報告 1.総務省北陸総合通信局、富山県、石川県、福井県、テレビ・ラジオ放送事業者、ケーブルテレビ事業者、通信事業者、ICT関連企業等37団体が参加し、検討した成果をとりまとめたものであること。 2.公共情報コモンズの導入に向けた実践的なマニュアルとして、今後、全国の地方公共団体等関係者が活用できるものとなっていること。 3.情報発信者である県・市町村が「公共情報コモンズ」に接続する形態として、防災情報システムの改修だけでなく、民間事業者が提供する「クラウドサービス」の利用を提案していること。 4.情報伝達者である放送事業者が「公共情報コモンズ」に接続する形態として、当面はコモンズビューワによる受信を推奨するとともに、データ放送システム等との自動連携を実現するための方策として、複数の事業者による共同利用サーバーの設置を提案していること。 5.北陸情報通信協議会安心・安全部会の今後の取組として、「公共情報コモンズ」に関する市町村向け説明会(北陸総合通信局と各県の連携により、各県別に開催予定)及び民間事業者による「クラウドサービス」のプロトタイプの開発、実証実験を支援することとしていること。 安心・安全部会は、今後、各県ごとに開催される市町村説明会を支援するとともに、部会内にクラウドモデルを検討するためのワーキンググループを設置することとしています。 |
| 第3回会合 平成24年11月6日 |
今回の会合では、民間事業者のクラウドサービスを活用する『公共情報コモンズ活用ソリューション』が提案されました。 これは、“現行の『防災情報システム』の改修時期に合わせないと、公共情報コモンズの導入ができない”という、多くの県・市町村に共通する課題に対応するもの(=市町村が防災情報システムを経由せず、かつ、安価に公共情報コモンズに接続できるようにするソリューション)であり、『防災情報システム』の改修時期がネックになっている多くの地域に対して、新たな選択肢を提供するものとして期待されます。 また、本部会の取組のまとめとして、『公共情報コモンズ』の導入に向けた報告書(案)が提案され、意見交換を行いました。 |
| 第2回会合 平成24年9月4日 |
「公共情報コモンズ」の導入に向けた課題の解決方策等に関し、8月に実施した部会参加会員(県、放送事業者及びケーブルテレビ事業者)に対する意向調査(導入のメリット、課題の認識等)の結果を踏まえ、また、公共情報コモンズの運営主体である一般財団法人マルチメディア振興センター(FMMC)の吉田正彦プロジェクト企画部長、川喜多孝之プロジェクト担当部長をアドバイザーに迎え、導入済み地域の事例なども参考にしながら、活発な議論を行いました。 |
| 第1回会合 平成24年7月4日 |
金沢大学理工研究域環境デザイン学系 教授 宮島 昌克 様を部会長に選出しました。 その後、宮島部会長から「北陸における地震津波災害と防災」と題する講演、NTT西日及びNTTドコモから大規模災害時等緊急時への対応等の紹介を受け、災害情報伝達の現状と課題についての整理を行いました。 |
モバイルサイト
北陸情報通信協議会モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!